本文
北伊予の伝承-13 (平成28年3月) 御祈祷(各地区ごと) 御祈祷とは
発行:
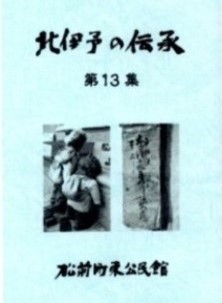
御祈祷とは
御祈祷(ごきとう)は、組祈祷ともいい神職か住職を迎え組中(くみじゅう)安全、家内安全、五穀(ごこく)豊穣(ほうじょう)を祈願し、組中の行事の決定や役員を選出し懇親会を行う新春の年中行事である。ところによれば「氏神講」、「お日待(ひま)ち」といわれるが、ほぼ同じ行事である。表1のごとく北伊予九地区のうち八地区が御祈祷を行い、主に夏の宮祈祷と正月の寺祈祷がある。
現在、宮および寺祈祷の両用で行っている地区は、中川原、出作、鶴吉の三地区。現在、住職による寺祈祷のみで行う地区は、徳丸、神崎、横田、大溝、東古泉の五地区である。理由は不明だが、古くから永田地区は北伊予地区内で唯一、御祈祷が行われていない。

このように同じ北伊予地区内でも大字(おおあざ)により祈祷の方法や内容が異なるのは、藩政時代独立した「村」として自治活動や年中行事を行ってきたことによると考えられる。
今回、北伊予の伝承編集委員会では、各地区の御祈祷の経緯や現状についてまとめ、改めて北伊予地区の伝統行事である御祈祷を見つめ直したいと考えた。
かつて、広く行われていた「お日待ち(おひまち)」は、組中安全、家内安全、五穀豊穣を祈願し、前日から宿(個人の家)に組の住民が集まり、夜通(よどお)し寝ずに話したり、酒を飲んだりして時を過ごし、日の出を待って祈祷した行事である。江戸時代にできたといわれ、農作業、慶弔(けいちょう)行事など、すべて講中(こうちゅう)(組)単位で行われていた組中仲間のコミュニケーションを図る大切な場であった。「お日待ち」が終わると「四方札(しほうふだ)」(境札(さかいふだ)、関札(せきふだ))と呼ばれる四枚のお札を村(組)の東西南北(境・関)に悪病等が入り込まないように立てた。四方札とは、北(多聞天(たもんてん))、東(持天(じこくてん))、西(広目天(こうもくてん))、南(増長天(ぞうちょうてん))を守護する四枚のお札である。名称は様々だが、現在も各地区で行っている。
 写真1 神職による御祈祷(出作地区)
写真1 神職による御祈祷(出作地区)
 写真2 住職による御祈祷(神崎地区)
写真2 住職による御祈祷(神崎地区)
時が流れ、住宅事情、職業や価値観の多様化、信教の自由など、住民の生活様式や意識の変化に応じて、元来の御祈祷の内容から大きく変容してきた。とくに実施日、場所、賄(まかない)など、共同体としての色彩が薄れ簡素化が進行している。近隣関係が希薄化(きはくか)しつつある今こそ、コミュニティ作りの場として御祈祷の重要性を見つめ直す時かもしれない。
なお、各地区の概況で記した世帯数や人口などは、大字区長から提供された今年の資料を使用した。
PDF版ダウンロード H28-北伊予の傳承13 [PDFファイル/12.83MB]



