本文
北伊予の伝承-14 (平成30年3月) 1 座談会 戦後70年 北伊予のくらしを辿る その2-昭和30年代から平成初期までのくらし- 2 昭和60年代のバブル期から平成10年までのバブル崩壊後のくらし
発行:
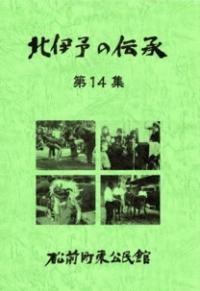
1 座談会 戦後70年 北伊予のくらしを辿る-昭和30年代から平成初期までのくらし-
2 昭和60年代のバブル期から平成10年までのバブル崩壊後のくらし
昭和六〇(一九八五)年以降の財テクブームで資金が土地や株式に集中し、バブル(水泡(すいほう))と呼ばれる実態経済を伴わない資産価値の上昇が起こり、株式が史上最高値を記録し未曽有の好況を迎えます。しかし、平成改元(一九八九)から一〇年余りの間にバブルが崩壊し、一転して平成不況期を迎えます。
司会 これからは低成長期からバブル崩壊までのくらし、すなわち昭和六〇年代のバブル期から平成一〇年頃までの豊かさを問い直す時代からバブル経済の崩壊後までについてお話ししていただきたいと思います。年代・職種・仕事の内容・役職等によって違いはあろうかと思いますが、自分たちにどんな影響があったのかバブル期の思い出についてお願いします。
(一)バブル期の思い出
三好 私は不動産の免許を持っていまして多少不動産をやっていましたが、ちょうど坊っちゃんスタジアムがある松山の中央公園ができる頃でしょうか、あの頃が土地価格のピークでバブル期でした。土地を売った関係者たちが代替地(だいたいち)として重信川を渡って北伊予側へ土地を求めて買いに来たんです。どうしても欲しいと言うので最後に値ように買うた人が、国近(くにち)川の源流、泉の所の農地を坪(三・三平方メートル)十万円で買ったのが私の記憶では最高額でした。その時の中川原の分譲地が坪四二、三万円で売りよりました。現在、農地は坪一万円でもなかなか売れません。それくらい急激に変わるとは夢にも思いませんでした。
それと株式の関係ですが、私もずっと親の代から農業を八反(八〇アール)ほどやっていましたので農協の理事・監事もさせていただきました。私が監事の時でした。資金の関係で農協はもともと株式を持つことはができなかったのですが、それが緩和されて農協も株を持ってもかまわなくなりました。それで農協も株の売買を始めたのですが、平成六(一九九四)年からバブルが弾け、株が暴落し大変な損害を被りました。いろいろな意味で世の中がこんなに変わるとは夢にも思いませんでした。
司会 今、土地の問題が出ましたが外にもありますか。
神野 私はサラリーマンでしたので景気がよくなって仕事がどんどん増えてきました。昭和四五年頃全国を回ったんですけど、モーレツ社員という言葉もありましたが、残業も月に二百時間くらいする時もしょっちゅうありました。ただ、私の場合は仕事(工場に新設した電気施設・設備の試運転調整)に対する誇りや愛着がありましたから、さほど苦痛ではなかったんですけど、反面、この間ずっと家を出ていましたので、家庭のことは全く放ったらかし状態でした。家に帰るたびに子どもは大きくなっているという状態もありました。悲しい面もありましたが、この時期は充実した生活であったかと思います。家庭の子どもや女房に対しては十分なことができなくて申し訳ないという気持ちも持っています。
司会 今、モーレツ社員という懐かしい言葉も出てきましたが、仕事もいろいろあった中で関連してどうでしようか。
八束 昭和五〇(一九七五)年に教員になりました。公務員ですから民間のようなバブルの影響はなかったんですが、時の総理大臣のお陰で一〇年間くらい給料がどんどん上がりました。年末の一二月は給料、ボーナス、年末調整などがあり、こんなにもらっていいのかと思うほどでした。
教員の仕事については今も新聞紙上をにぎわしているように負担が大きくなっているということですが、私たちが若い頃は朝七時には学校に行っていました、体育館や運動場を開けて、校門を開けたら生徒たちがやってきます。一時間の朝練、八時から授業をして、授業が終わって、冬と夏とは違いますが暗くなるまで部活を見て、それから自分の仕事をして家に帰ると一二時間以上は学校におりました。土曜・日曜日は練習試合、休みと言えば盆と正月くらいでした。このことが今問題になり社会問題になっています。仕事は精一杯したんですが、その代り家庭は一人親家庭みたいなものでした。
三谷 私も教員でしたのでバブルだからとか不景気だからとかということで私自身の給料はあまり左右されなかったので特にはないんですが、ただ覚えているのが預金の金利で、バブルの時期の定期預金で一番よかった時が年八パーセントでした。何年だったか忘れましたが、今の金利は大変低くてないようなものですが、当時の金利八貿パーセントという数字だけは記憶に残っています。
司会 職種によっていろいろあったと思いますが。
小田原 農業に関してお話したいと思います。農家所得は米の価格が上がらなかったから減ってきました。私か昭和五〇年にJAに就職してからずっと動向を見ていると、昭和四八年くらいからオイルショックがあって、トイレットペーパーとか洗剤不足があって減反政策が始まった。今も続いていますが四り年近くになりますが、その問の米の価格は下がる一方で、逆に農機具は高性能化し価格は上がっています。私も臨時税理士の資格を取って四〇年間ほど農業所得について二百名くらい診ていました。そしたら農家の人から言われるんです。「小田原君、わしゃ借家の不動産収入がなけりゃ生活ができんが」、「農協へ肥料や農薬の購買代金を払いに来るのに年金をを持ってこな払えん」とか「農協からもらえるかねは通帳に入っているこれだけしかない」とよく聞かされました。米価が下がったのが根本的な原因だと思います。就職した時期は、米が一キログラム四百五十円、喫茶店でコーヒーを飲むと三百円から四百円くらい。たとえが悪いかもしれませんが、米一キログラムとコーヒー一杯が一緒かと。それくらい米の価値が下がってきた。米を作っておられる方もおられますが、問題なのは農家が自分で作った農産物の値段を自分で決められんことです。
最近は新しい傾向で直売所ができてくると、そこでお客の欲しいもの・ニーズに合わせて作って、その代りこの値段ですよと言って自分で価格を決めて売る。言えば自分の作ったもの、自信を持って作ったものに自分で値段を付けて売る、こういう新しい流れも出てきています。お米の話をしましたが、ミカンも一緒で昭和五四(一九七九)年くらいから量がダブついてきて減反政策が始まり、ミカンの樹を切れば一反(一〇アール)五万か八万円の補助金が国から出ました。
栗原 今、小田原さんが話した通りだと思います。米価が上がらなかったと言うより、まだ下がっていますよね。国民の主食である米の価格が下がることは消費者にとっては生活しやすいと思いますが、それでは農家の経営は維持できないと思います。その辺の改革がないと農家はやっていけません。農家の戸数は減ってきていますし、高齢化も進む中で五年後、一〇年後はどうなっているのか、皆さんの食料も自給できないかもしれません。
最近、企業が農業分野に入ってきていますけど、もうけるところはもうけています。やり方・工夫次第で大分違うようです。もうかる農業のキーワードが健康志向と体験型農業だそうです。実際、体験型農業を取り入れている所なんかは、農家がすることを一般の人にやってもらってお金を頂いている。やり方次第だそうですが、実際知恵が回らないので現状維持で苦労しています。これからの農業が明るい未来になるよう願っています。
渡部 バブルの時期から今でも農業は困っています。国民の主食であるお米が安いということは国民にとっては生活がしやすくよいことで、国の安全保障を考えた場合、食の安全が大事で主食である米だけは大事にしておかないといかん。
私の所も今は私か農業をしていますが後はどうなるかわかりません。北伊予地域を考えた場合、北伊予は昔から農業地帯ですが、生活していくためには農業だけではいかんぞということで、どこかに働きに行ける雇用の基盤が安定していたら働きながら農業もやることもできる。定年になって退職したら農業ができるようにしてもらいたいし、農業を大事にしてもらいたいと思っとります。
(二)バブル崩壊後
司会 昭和六〇(一九八五)年以降、次第にバブル経済期が終わり、バブル崩壊後不況時代が到来しました。この時期をどう乗り切りましたか。
巻幡 サラリーマンの妻ですので、あまりバブル崩壊の実感はありませんでした。ただ子どもたちが就職氷河期に当たり大変苦労していました。
三好 バブル崩壊後から大手のハウスメーカーが積極的にモデル住宅の展示場を設置して宣伝・営業販売に力を入れてきました。若い世代の家はほとんどその方へ流れて、大工さんの家は減少しました。そうした中でも北伊予地区は農家も多く本家(母屋)の新築はスギ・ヒノキなどの良質の木材を使用し、日本瓦葺の在来工法の家や長屋門がぽつぽつ建ち、私の製材所はなんとか維持しましたが、平成七(一九九五)年に町議に出てからは縮小しながら廃業しました。
稲垣 私は生来慎重派で、こんな実態のない経済社会が長続きするとは思えませんでした。お陰さまで株式、その他ギャンブル性の高いものに対してはいっさい手を出さず、従って損得にからむ苦い経験もありません。友人、知人の中には、ご多聞にもれず株式、土地、その他不動産に手を染めて、資産価値のな
い物件を押し付けられた人、借りた金を全部株式に投資してバブルが弾けたとたん、手元に残ったのは莫大な借金だけの人もいました。バブルからは多くのことを学びました。
三好 少し内容が違うと思いますが、この際お知らせしたいと思います。
昭和六三(一九八八)年、竹下総理大臣の時ですが、「ふるさと創生事業」が行われ、交付金が自治体の大小にかかわらずすべての市町村に対して一律に一億円支給されました。それぞれの市町村においていろいろな使われ方をしました。高知県では黄金の鰹像を作り、それが盗まれたりして話題になりましたが、松前町では先ず中川原のひょこたん池公園から、続いて神崎・鶴吉の福徳泉公園、大間の有明公園の整備に使いました。この事業は住田町長から白石町長へと引き継がれました。このことは強調しておきたいんですが、後世に残る本当に素晴らしい使い方をしたと思っています。
 写真24 ひょこたん池公園(中川原)
写真24 ひょこたん池公園(中川原)
 写真25 福徳泉公園(神崎・鶴吉)
写真25 福徳泉公園(神崎・鶴吉)
(三)真の豊かさとは
司会 バブルの時代が過ぎ、「豊かさとは何か」を問い直す時代が到来しています。皆さんはどう思いますか。
村上 真の豊かさは、人それぞれ価値観が違いますから一概には言えませんが、自分の心の持ちようにあると思います。家族仲よく、地域の皆さんと声かけあって助け合うことができるように、そして大勢の人との出会いを大切にして生活できるように心がけていくことが、真の豊かさにつながるように思います。
稲川 もちろん経済的豊かさが、そのすべての根幹になるとは思いますが、それだけに頼り過ぎると味気ない人間味のない社会が構成されていくと思います。この世で生きていく限り、お互いを尊重し、よりよい人間関係を築いていくことが大切なのではと思います。「真の豊かさ」とは「心の豊かさ」ではないでしょうか。
巻幡 家族が仲よく、健康で暮らせたら、幸せだと思っています。とにかく普通がいちばん豊かなことだと思います。
鎌倉 物の豊かさだけでなくて、他人の気持ちを推し量りながら、思いやりを持って接するという心の豊かさだと考えています。
三好 六〇数年前になりますが、子どもの頃を思い起こしますと、同居していた祖父母から、物を大切にすることとか、生活態度や人間性なんかを厳しく躾けられましたね。近所の方々とはいろいろな物を譲りあって暮らしていました。
現在は物が豊かになってIT(情報技術)が急速に進歩して大変便利になりましたが、その反面個人の考え方や価値観がしだいに変わってきました。個人主義的な考え方が強くなってきましたし、少子高齢化が進んで独居の高齢者が増えていると思います。また一般常識では理解できないようなことが次々と起こって心配です。だからこそ家庭も地域もそれぞれが人情豊かに触れ合い、支え合う「共創・共感・共生」の社会づくりが必要じやないでしょうか。「真の豊かさ」とは、「心」と「物」の両面が豊かであることだと思います。
PDF版ダウンロード H30-北伊予の傳承14 [PDFファイル/10.67MB]



