本文
北伊予の伝承-13 (平成28年3月) 御祈祷(各地区ごと) 御祈祷(各地区ごと)
発行:
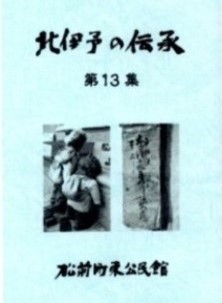
御祈祷とは
御祈祷(各地区ごと)
「御祈祷」のまとめを終えて
北伊予地区では、永田地区を除く八地区で「御祈祷」が行われているが、その内容は、地区(大字(おおあざ))や同じ地区内でも組によりかなり異なるため、私たち北伊予の伝承編集委員会では、各地区の御祈祷の起源や現状などについて、古文書や聞き取りなどから、改めて現状を見つめ直した。
まず、文政年間(1820年頃)に「大般若波羅蜜多経」六百巻を徳丸・神崎・鶴吉などで祈祷用に購入したことや「入用帳」の記録などから、その頃が起源と考えられる。
また、実施内容を見ると、地区によってかなりの違いが見られるのは、かつて大字は藩政時代、松山藩の「村」であり、独自の自治活動や年中行事を行ってきたことによると考えられる。御祈祷は、ところによれば「氏神講(こう)」や「お日待(ひま)ち」と呼ばれた。
北伊予地区内で、現在、宮および寺祈祷の両方で祈祷を行っているのは三地区のみである。宮祈祷は田休み時期に神職を迎え行うが、大方の地区では消滅している。他は新春に住職を迎えて行う寺祈祷が中心をなす。
新春の御祈祷は、かつては「お日待ち」として、二日間個人の宿元で行なわれていたと思われるが、現在行っている地区・組はない。
時代の進行にともない、実施内容も大きく変容してきた。
その変容は、藩政時代から「入用帳」や「宿覚書」などに脈々と書き記(しる)された資料などからも明らかである。特に実施日や祈祷内容、組会、そして組内のコミュニケーションを図(はか)る懇親会やその賄い方も大きく簡素化してきた。
近隣関係が希薄化しつつある今こそ、本来の御祈祷の趣旨を改めて見つめ直し、継承していきたいものである。
PDF版ダウンロード H28-北伊予の傳承13 [PDFファイル/12.83MB]












