本文
北伊予の伝承-14 (平成30年3月) 季節を彩る北伊予の祭礼 -まつり- 徳丸
発行:
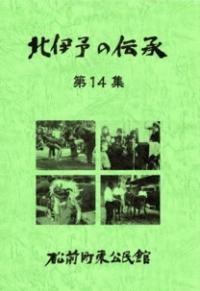
季節を彩る北伊予の祭礼-まつり-(各地区ごと)一 徳丸
(一)徳丸の祭り
徳丸は、高忍日賣神社(たかおしひめ)の氏子である。高忍日賣神社の創立年代は不詳(ふしょう)であるが、飛鳥(あすか)時代に聖徳太子が道後に来られた際に参詣(さんけい)され、神号(じんごう)扁額(へんがく)を奉納されたという。また、平安時代に醍醐(だいご)天皇の命により定められた延喜式(えんぎしき)に記載された神社(延喜式内社)である。徳丸の歴史は高忍日賣神社の歴史と深い関わりがある。
(二) 春祭り
徳丸の春祭りは、毎年四月二九日(昭和の日)に執り行われる。春祭りは、五穀豊穣(ごこくほうじょう)を祈念するお祭りで、高忍日賣神社と境内末社素鵞(そが)神社(天王(てんのう)さん)にて祭典が斎行(さいこう)される。
 写真1 春祭奉納相撲(平成24年4月29日)
写真1 春祭奉納相撲(平成24年4月29日)
また、中学生以下の子どもたちによる奉納相撲がある。純真無垢(むく)の子どもたちが、土を力強く踏みしめて相撲を取ることにより、土の神様がお喜びになり、豊作がもたらされるのである。祭典の前に、拝殿において皆でお祓いを受け相撲を取る。中学生が中心となって、土俵作りや行司(ぎょうじ)などの相撲の運営を、責任を持って行っている。また、愛護部を始め文化部や、そのほか徳丸の有志も協力して中学生たちがきちんと運営できるよう支えている。そして、大人も子どもも一体になって、大いに盛り上がっている。地域社会の本来の姿がここにある。地域の後継者としての子どもたちを育てるため、地域住民が互いに関わりあい、賑にぎやかな春祭りとなっている。
(三) 虫干祭
徳丸の夏祭りは、虫干祭(むしぼしさい)である。毎年八月二日に行われる賑にぎやかな祭りである。
日本人は、古来より災厄(さいやく)は、心や体に付いた「けがれ」によってもたらされるものとして、日頃より心を清浄に保ち体に付く様々な「けがれ」を落とすことが必要であり、そこで「禊(みそぎ)」や「祓(はらえ)」を行うのである。それは、古事記や日本書紀に、イザナギノミコトが死者の国である黄泉(よみ)の国くにから逃げ帰り禊をしたという話からも分かる。神社では年の前半、つまり元日から六月三〇日と、後半の七月一日から大晦日(みそか)に分け、六月三〇日と大晦日に大祓式(おおはらえしき)を斎行するのである。このうち、特に六月三〇日には茅(ちがや)で輪を作り茅ノ輪(ちのわ)、それをくぐることにより茅で心身のけがれを断ち切り、無事に夏を越せるのである。ここから一般に「夏越祭(なごしさい」とか「輪越祭(わごしさい)」と呼ばれる。
 写真2 虫干祭神事(平成29年8月2日)
写真2 虫干祭神事(平成29年8月2日)
虫干祭当日、午前一〇時より祭典が厳かに執り行われる。祭典の中で、拝殿祓所の前で神職・総代に「ひな形」が配られ、それで体をなでて息を吹きかけ、それを持って茅ノ輪くぐりの神事が行われる。宮司に従って一列になり和歌を唱えながら茅ノ輪を左右左とくぐり、最後に秡所の前において「大祓詞(おおはらえことば)」を一斉に唱え、「けがれ」を祓う。
高忍日賣神社は、かつてはこの祭りに神御衣(かんみそ)(神様の衣)などに風を通す虫干しをしていたことから「虫干祭」という名が付いたといわれる。氏子・崇敬者(すうけいしゃ)は祭りの当日、「ひな形」を持って神社の茅ノ輪をくぐり、拝殿の祓所で神職によるお祓いを受ける。最後に御神札(おふだ)をいただいて帰る。いただいた御神札は、家の戸口に貼り、災いから守っていただく。
さて、祭りの夜の境内は露店などが並び、特設舞台では、氏子の有志によるカラオケや踊りの披露、徳丸一座(徳丸村芝居実行委員会)による村芝居(人情時代劇)が上演される。氏子内外の参拝者で賑わう。ちなみに平成二九年は「勘太郎月夜唄」が上演され、村芝居復活後第二二回となっている。虫干祭では戦前から青年団が芝居や踊りを披露して祭りの夜を盛り上げていたが、戦後の高度経済成長期に若者の減少により青年団がなくなり、村芝居が途絶えた時期があったが、平成八(一九九六)年に、当時の青年有志と宮司や徳丸・中川原・大間(だいま)の宮総代らが協力し合って、村興(むらおこし)にも繋(つな)がるとして村芝居を復活させたのである。
 写真3 奉納村芝居(平成20年8月2日)
写真3 奉納村芝居(平成20年8月2日)
復活初演の舞台に立ったA氏はその時のことを、「舞台の材料を揃えたり、演目や脚本、芝居の指導者である師匠捜し、大道具や小道具作り、スタッフ募集などはもとより、役者としての台詞(せりふ)や所作(しょさ)を覚えたり、大変な苦労を重ねて、やっと迎えた初演本番の極度の緊張の中で、無事成功を収めた感動は今でも忘れられない。」と話してくれた。
毎年虫干祭の公演で多くの人々に感動を与え続けている村芝居ではあるが、舞台裏の事情は大変なところがある。
スタッフのB氏は、「約三か月の稽古(けいこ)期間を要するが、スタッフは仕事もあり、全員揃そろっての稽古がなかなか出来ないし、衣装などの費用のことや人手不足の苦労も大変という現状もある。」と話してくれた。
(四) 例大祭(秋季大祭)
例大祭は一年の祭りのうちで最大の祭りである。松前地方の秋祭りは毎年一〇月一三日の宵祭りに始まり一五日の神輿渡御(しんよとぎょ)で祭りのクライマックスとなる。
例大祭と切っても切り離せないのが、獅子舞(ししまい)と神輿の渡御(巡幸)である。その内、獅子舞は大切な伝統芸能で、獅子舞の練習の太鼓の音が聞こえてくると秋の深まりを感じる風物詩ともなっている。
一〇月一二日の早朝、一斉に幟(のぼり)が立てられる。例大祭では、今年の五穀豊穣を氏神様にご覧になっていただき、感謝申し上げ、神様と人々とが共に豊作を喜び祝うのである。高忍日賣神社では、一三日の宵祭りに徳丸・中川原・大間(だいま)の神輿が並び、徳丸と中川原の獅子舞が奉納される。現在獅子舞は、かつて上組、西組、下組の三つあったが、現在は二つのグループが続いている。そして、それぞれ「獅子舞保存会」が作られ、子どもたちに熱心に獅子舞を教え伝えている。舞い方にもグループによる違いがあり、興味深いものがある。獅子舞の奉納は、午後七時三〇分頃に高忍日賣神社拝殿に集まり、お祓いを受けた後に行われ、午後九時過ぎまで行われる。
また、子どもたちは、高張提灯(ちょうちん)を持ち、組中(くみじゅう)の家々で「おたふく(おたやん)がまいこんだ」と言いながら回り、菓子などを貰もらう。一四日の夜も回るのであるが、家に入った時には「おたふくがまいこんだ、おたふくがまいこんだ」と言うのは同じだが、家から外へ出たら「らいねんじゃぁ、らいねんじゃぁ」と唱えるのである。
一四日には、拝殿に三体の御羽車(おはぐるま)と徳丸、中川原、大間の計五体の神輿が並び、祭典が厳かに斎行される。また、夜には浄闇(じょうあん)の中、御霊遷し(みたまうつし)の神事が斎行される。
 写真4 神輿渡御、御旅所までの行列
写真4 神輿渡御、御旅所までの行列
猿田彦命が先導する
(平成28年10月15日)
 写真5 神輿渡御、御旅所神事 こののち神輿は各地区へと別れて巡幸する(平成27年10月15日)
写真5 神輿渡御、御旅所神事 こののち神輿は各地区へと別れて巡幸する(平成27年10月15日)
翌(よく)一五日は、午前六時に発輿祭(はつよさい)(宮出し神事)が斎行され、徳丸、中川原、大間の神輿の渡御が始まる。先ずは神社から一丁地(いっちょうじ)の御旅所まで猿田彦命(さるたひこのみこと)の先導で行列して向かう。猿田彦命とは、天孫(てんそん)ニニギノミコトが高天原(たかまがはら)から日向(ひゅうが)の国(くに)高千穂(たかちほ)の峰(みね)に下られた際、道案内をした神様である。この故事にちなんで、御旅所までの行列の先頭に立って歩くのである。猿田彦命役は、氏子の中から四二歳もしくは六一歳の男性から選ばれる。行列が動き出すと、ちょうど朝日が東の山から顔を覗のぞかせ、その光が神輿の屋根に当たって鳳凰(ほうおう)が輝き神々(こうごう)しく美しい。御旅所に着くと、神事が斎行され、小学三年生から五年生の女子の中から選ばれた巫女(みこ)が鈴神楽(すずかぐら)を舞う。神事が終わると、神輿はそれぞれの地区に向かい、巡幸するのである。徳丸では、大小二体の神輿が賑やかに勇壮に各組を渡御し、夜には高忍日賣神社に宮入りする。神輿の周りには、老若男女が集まり、各組の辻や新しく建った家などにかき据すえ、更に獅子舞もあったりして、大変な賑わいである。ほぼ一日かけて徳丸中を回る。
お宮の隣の徳丸老人憩いの家の前では、徳丸婦人部の協力でうどんが振る舞われ、うどんで腹ごしらえの後、宮入りとなる。まさに地域挙あげてのお祭りであり、神様と人々が共に喜びを分かち合う大切なお祭りである。
(五)その他の祭り
その他の祭りとして、一月には歳旦祭(さいたんさい)、元始祭(げんしさい)、日供始祭(にっくはじめさい)、どんど焼き、二月には節分祭、祈年祭、紀元祭、五月は尚歯会(しょうしかい)神事、八月は戦没者慰霊祭、九月は諏訪(すわ)神社例祭、夷子(えびす)神社例祭、一一月は新嘗(にいなめ)祭、一二月は大祓式、除夜祭がある。
このうち、諏訪神社例祭、夷子神社例祭、尚歯会神事、戦没者慰霊祭について述べる。
1 諏訪神社例祭
九月の諏訪神社例祭は、境内末社諏訪神社の祭りで、諏訪神社はかつて徳丸河原組にあったが、明治の合祀令(ごうしれい)により、境内末社の素鵞神社に合祀されている。祭礼日は毎年九月一七日で、祭典には河原組の組長さんが参列し執(と)り行われている。五穀豊穣と組中の安全に感謝申し上げるのである。
2 夷子神社例祭
夷子神社は、高忍日賣神社の鬼門(きもん)と裏鬼門を守る社(やしろ)として、奈良時代から祀られている神社である。神社から直線で北東方向と南西方向に三百mくらい離れた場所に鎮座(ちんざ)していた。そして、社を中心に市いちが開かれ、中世には大変賑わったと言われている。北東方向にある夷子神社を上市(かみいち)えびす、南西方向にあるのを下市(しもいち)えびすと呼んでいたらしい。下市えびすは明治の合祀令によって高忍日賣神社境内の素鵞神社に合祀されている。上市えびすは、長い歴史の中で市の衰退とともに個人の屋敷内に取り込まれていたために合祀令を免まぬかれ、最近まで本来の場所に鎮座していた。しかし、鎮座していた屋敷の持ち主のやむを得ない事情もあり、高忍日賣神社境内の東北隅に遷座(せんざ)して現在に至っている。仮遷座祭は、平成一九年一月の夜中に浄闇の中行われ、その行列を地元の表、裏組の人々が手を合わせて見送っていた姿がいかに多くの人々にえびす様が慕したわれていたかを物語っている。かつての社は、庚午石(こうごいし)と呼ばれる粒の小さい礫岩(れきがん)で作られ、時代は室町時代らしい。風化して崩れたので現在は木造の社となっている。
 写真6 夷子神社例祭(平成29年9月18日)
写真6 夷子神社例祭(平成29年9月18日)
ここで言う夷子神社例祭とは、この上市えびすのお祭りで、毎年秋の社日(しゃにち)に執り行われる。元田中組(表組、裏組)の組長さん始め、宮総代、区長、御先号に遷宮(せんぐう)に関わった世話人の方々が参列している。社日は、春の社日と秋の社日があり、それぞれ春分、秋分に最も近い「戊(つちのえ)の日」のこと。豊かな実りを感謝するお祭りだが、商売繁昌や家運の隆昌を祈るお祭でもある。
3 尚歯会神事
尚歯会は、「郷土の発展は老人の積み重ねし努力の成果なり」として、大正二(一九一三)年五月一六日に、高忍日賣神社が主体となって第一回の徳丸尚歯会が催された。毎年五月の第二日曜日(母の日)に徳丸の数え七五歳以上の高齢者を大字徳丸役員が招待して、高忍日賣神社で神事を執り行い、老人憩いの家で祝宴を催す行事である。
戦時中も脈々と敬老の精神は受け継がれ、戦後は物資欠乏や物価高騰(こうとう)などにより、会費や寄付金では会の運営が危ぶまれたが、昭和二七(一九五二)年の第四〇回をもって神社から大字徳丸に移管され、昭和二八年からは大字徳丸主催の行事となった。平成二四年で百周年を数え、現在に至っている。他にこれほど続いている地域は珍しいのではないだろうか。徳丸の敬老の精神を受け継ぐ大切な伝統行事となっている。
4 戦没者慰霊祭
高忍日賣神社境内の「慰霊之塔(いれいのとう)」には、高忍日賣神社の氏子出身で、日清戦争から太平洋(大東亜)戦争にかけて、国のために出征し戦って亡くなられた百十二柱の英霊が祀られている。
東公民館の西側の忠霊塔に北伊予出身の英霊が祀られ、かつては慰霊祭も行われていたようであるが、それが出来なくなり、太平洋(大東亜)戦争終戦三〇年を記念して復員者一同が発起人となり、高忍日賣神社慰霊之塔奉賛会を組織して浄財(じょうざい)を集め境内に「慰霊之塔」を建て高忍日賣神社氏子出身の英霊を祀ることになったのである。
 写真7 戦没者慰霊祭(平成28年8月15日)
写真7 戦没者慰霊祭(平成28年8月15日)
昭和五〇年八月一五日、遺族を招待して第一回慰霊祭を斎行した。以来、毎年八月一五日の終戦記念日に慰霊祭を執り行っており、現在は神社総代が奉賛会の世話をしている。近年、遺族の数も減り、出席者も少なくなっているが、慰霊祭は続けていきたいと考えている。
PDF版ダウンロード H30-北伊予の傳承14 [PDFファイル/10.67MB]












