本文
北伊予の伝承-14 (平成30年3月) 季節を彩る北伊予の祭礼 -まつり- 東古泉
発行:
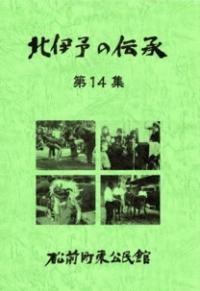
季節を彩る北伊予の祭礼-まつり-(各地区ごと)九 東古泉
これから記す文章の内容については、次の方々に御協力をしていただいた。玉生八幡(たもうはちまん)大神社宮司の武智和孝さん(昭和二四年生まれ)、東古泉の早瀬哲夫さん(昭和五年生まれ)、三好國榮さん(昭和一七年生まれ)、早瀬武臣さん(昭和二〇年生まれ)、三好重敏さん(昭和二三年生まれ)、高市清則さん(昭和二三年生まれ)、三好則雄さん(昭和二七年生まれ)。
また、各種資料については、主に『松前町誌』と『北伊予の伝承』を利用引用した。なお、写真はすべて平成二九年撮影したものを使用した。
(一) 地区の概況と氏神さま
北伊予地区の最西部に位置し、松前地区や岡田地区とも接する地域である。古くから豊かな水の湧き出ている里で、「稲納屋(いなや)」とも呼ばれていた。記録によれば、元文三(一七三八)年、古泉村が分かれて、東古泉村と西古泉村とになった。東古泉村は明和七(一七七〇)年には五七戸、昭和五二(一九七七)年には一三四戸であった。平成二九年四月現在、東古泉の組数は一〇組、世帯数は二三〇戸で人口は五六〇人である。
氏神さまは、大字(おおあざ)東古泉一ノ関にある素鵞(そが)神社で主祭神は建速素盞嗚命(たけはやすさのおのみこと)、配神は日速彦命(ひはやびこのみこと)である。素鵞神社の宮司は大字西古泉にある玉生八幡大神社の武智和孝宮司が兼務している。素鵞神社は、古来東古泉の人々から尊崇され鎮守(ちんじゅ)の神さまとして、「天王さん」の名で親しまれている。
 写真1 素鵞神社(東古泉)
写真1 素鵞神社(東古泉)
 写真2 玉生八幡大神社
写真2 玉生八幡大神社
(二) 季節を彩る祭り
1 春祭り
農作業の始まる時期に、秋の豊作を祈って行われる春祭りは四月二九日に開催される。当日の朝、素鵞神社において玉生神社の武智宮司を迎えて関係者で神事を行う。神事が終わると、春祭りの伝統行事である子どもたちによる奉納相撲大会が素鵞神社東側のコミュニティ広場で催される。従来男子だけの相撲大会であったが平成四年からは男女参加の催しになっている。その模様は『北伊予の伝承9』の「春祭り」にイラスト入りで記載されているので、ここでは割愛(かつあい)し、今年の春祭りの写真を掲載する。午後からは東古泉地区の運動会が行われる。
 写真3 神事(素鵞神社)
写真3 神事(素鵞神社)
 写真4 奉納子ども相撲
写真4 奉納子ども相撲
2 夏祭り
春秋の祭りとはその起こりが多少異なり、悪疫(あくえき)退散の祈願から発生したと思われる夏祭りは、東古泉では七月二三日に開催される。氏子たちによって素鵞神社にお祭りを知らせる幟(のぼり)が立てられるが、そのほかには夏祭りとしての大きな催しや行事などは行われていない。毎年夏に行われている伝統行事としては、氏神さまの玉生神社で八月一日に催される茅(ちがや)の輪をくぐって潔斎(けっさい)し疫病や災難を祓(はら)う「輪越」の行事がある。その様子は『北伊予の伝承9』の「輪越(玉生神社)」に掲載されているので、ここでは割愛する。
3 秋祭り
豊かな収穫を祈念し、無事に過ごせたことを神さまに感謝して行う秋祭りは一〇月一三日の宵祭りに始まり、一四日、一五日と東古泉全域で行われる。一二日の早朝、素鵞神社をはじめ五か所にそれぞれ二本ずつの幟が立てられ、要所に御神燈が準備される。秋祭りの行事としては、平成二〇年から大字の公民館活動の一環として愛護部が中心となって実施している高張(たかはり)提灯(ちょうちん)と子ども神輿(みこし)巡行、そして同じく公民館活動の一環として獅子舞(ししまい)保存会が実施している獅子舞がある。
(1) 高張提灯
もとは玉生神社からお光を頂き、そのお光でともした提灯を掲げて大字を回り、神さまの御神威(ごしんい)と御神徳とを家々にお届けするのが高張提灯である。また祭事において火にはお清めの意味があり、これを持って歩くことで、地域のお清めをし、その灯り(あか)で神さまの神輿での巡行の道筋を知らせる役割があるとされる高張提灯は、一三日、一四日の午後六時頃から行われる。以前は子ども会の行事として中学生と小学生の男子全員が素鵞神社を出発し、一三日は大字の主要道路を、一四日は各家々を回っていた。男子生徒全員が高張提灯を持ち、ろうそくに火をともして高く掲げ「詣(もう)で来い」の意とされる「モーテーコーイ、モーテーコイ。」を大声で唱えて歩く。家に着くと広い土間に入れる限りの子どもたちが入り「ワーッ」と一斉に提灯を高く掲げ「ワッショイ、ワッショイ」と唱えながら家を後にしていた。
その後、平成四年から男子だけでなく女子も参加するようになり、回り方も一三日は上の組の各家々、一四日は下の組の各家々を回るようになっている。以前とは変わり乾電池で豆電球をともした提灯や懐中電灯、LEDライトなどを持っての高張提灯になっているが、「モーテーコーイ、モーテーコイ。モーテーコーイ、モーテーコイ。」と大声で唱えながら回っていく。こうして高張提灯は、今も大字内を清め神さまの御神威と御神徳を大字内に届け広めて一五日の子ども神輿巡行に備える。
 写真5 高張提灯
写真5 高張提灯
(2) 獅子舞
獅子舞は、大陸から伝わり、舞楽として演奏したものであるが、後に変容して太神楽(だいかぐら)や各地の祭礼などで、五穀(ごこく)豊穣(ほうじょう)の祈祷(きとう)や悪魔払いとして、新年の祝いや祭礼に行われるようになったものである。
東古泉の獅子舞は、大正か昭和の初め頃、有志七、八名で始められたのではないかといわれている。戦時中や昭和五〇(一九七五)年頃途絶えたが、その後やはり秋祭りには獅子舞がほしいという機運が高まり、昭和六三年有志十数名によって復活し現在に至る。そしてこの度、平成二九年度松前町コミュニティ助成(宝くじ助成)事業助成金交付を受け、獅子舞用具一式を更新し伝統行事をさらに継承していく運びとなった。一〇月八日素鵞神社において玉生神社の宮司を迎え獅子頭(がしら)入魂式の神事を行い獅子舞が奉納お披露目(ひろめ)された。
 写真6 獅子頭入魂式
写真6 獅子頭入魂式
 写真7 お披露目の獅子舞
写真7 お披露目の獅子舞
東古泉の獅子舞の内容は獅子の「舞」が最初にあり、続いて「いれは」を中に挟(はさ)み、もう一度「舞」を舞って終わる。これを「一庭(ひとにわ)」という。
秋祭りが近づくと、獅子舞の練習が始まり、毎晩保存会の会員や子どもたちが公民館に集まり熱心な練習が続く。
獅子の舞は軽やかで力強い大小の太鼓の囃子(はやし)に合わせて保存会の大人二人で舞うが、舞の中ごろに一番の見せ所「芸」と呼ぶ踊りがある。その踊りの違いによって、イモホリ・カラトビ・ヤマサガシ・ラン・シャミ・トクマル・ホンカン・ウソカンの八種の舞があった。しかし、現在舞われているのは五種類の舞でトクマル、ホンカン、ウソカンの舞い方は分からなくなっている。
獅子が舞い疲れて寝てしまうと、そこに小学生の扮する狩人が現れ獅子を起こす。獅子は怒って暴れ激しく舞うが、狩人によって退治される。
「いれは」は親爺(おやじ)と小学生の扮する子役の芸で親爺が猿と二匹の狐(きつね)を連れて、畑仕事に出かける。畑を耕し、鍬(くわ)で均(なら)し、種をまき、土をかぶせるがその間、猿は親爺の農作業の邪魔をし、狐は飛び跳ね遊びまわる。三者がいろいろと絡み合った後、親爺は畑仕事を終えて猿と狐を連れて家に帰り、一緒に夕飯を食べる。猿と狐たちはおとなしく夕飯を食べるが、食べ終えた途端、親爺を押さえつけ、「いれは」は終わる。
最後に初めの舞とは別の芸を獅子が舞い、舞った後疲れて寝てしまう。そこにまた狩人が現れ獅子を起こす。獅子は怒って舞い狂うが、狩人によって退治される。こうして悪魔祓いをして五穀豊穣と家内安全を祈願する「一庭」の獅子舞は終わる。
獅子舞の日程は、一三日の夜の素鵞神社への奉納獅子に始まり、一四日は要望のあった施設や商店などで舞われる。一五日は獅子舞いの関係者の家、大溝と永田と東古泉の舞い比べも行われるエミフルMasaki、その他新築の家や新たな転入者の家、希望者の家などで舞われ、最後はコミュニティ広場で舞い納める。
 写真8「いれは」を演ずる
写真8「いれは」を演ずる
 写真9 獅子の舞い比べ
写真9 獅子の舞い比べ
(3) 神輿
神さまのための乗り物である神輿は、御神体や御霊代(みたましろ)を載せて神社を出て地域を巡り、神社にお戻しするまでの乗り物である。東古泉では、その経緯や変遷はよく分からないが以前には大人の神輿がかかれていた。また、羽車(はぐるま)(庚申車(こうしんぐるま))は西古泉との共用で午前中は東古泉を巡行し、午後になると羽車は西古泉に引き継いでいた。その神輿も大人の担ぎ(かつ)手が少なくなったこともあり昭和三〇年代後半にはかかれなくなった。神輿は解体されたが、二本のかき棒は素鵞神社南側の幟棒などの収納場所に今も収められている。そしてその後は御神体を載せた羽車だけが巡行していた。昭和五四(一九七九)年大字で子ども神輿を新調し小、中学生の男子によって運行されるようになり、平成四年からは男女ともに参加しての子ども神輿巡行が盛大に行われている。
前の週から子どもたちや関係者で準備していた神輿を一四日の午後、玉生神社に「宮上げ」して御神体を神輿に移し、一五日の早朝「宮出し」をする。午前八時、神輿は素鵞神社を出てあらかじめ大字中(じゅう)に連絡されている経路に従って、賑(にぎ)やかに「祭り音頭」の音楽を流しながら巡行する。各家々では神輿が来ると、準備していた塩水を南天(なんてん)の葉でお祓(はら)いして散米し、お供米(くま)を二合(三百?)寄進する。また、お旅所や宿では神輿を据(す)えて神さまの御神威、御神徳を受け、様々な賄いをする。こうして神輿に載った神さまに神さまが守っている地域の様子を見ていただき、よろこんでいただくとともに感謝の心を伝える。お昼頃神輿は素鵞神社に還(かえ)り、愛護部の準備してくれた昼食をみんなで頂き休憩をする。その後中学生と関係者によって玉生神社への宮入りを済ませ、素鵞神社で後片付けをして神輿の行事は終わる。
 写真10 玉生神社への宮上げ
写真10 玉生神社への宮上げ
 写真11 雨の中の子ども神輿の巡行
写真11 雨の中の子ども神輿の巡行
4 四ツグロ大権現例祭
毎年一〇月一六日の朝、大字東古泉四つ黒にあって多喜津(たきつ)姫(ひめ)(瀧(たき)姫(ひめ))と三人の侍女たちが祀(まつ)られる四ツグロ大権現(四ツ黒権現社)に玉生神社の宮司を迎えて、関係者による例祭が行われている。その内容は『北伊予の伝承1』の「四ッグロ大権現」に記載されている。また、『松前町誌』の「瀧姫伝説と信仰」にも詳述されているので省略する。
写真12 四ツグロ大権現での神事
5 勤労感謝祭
勤労感謝祭は、もと新嘗祭(にいなめさい)から始まった祭礼で、新嘗祭は新穀を神にささげて収穫を感謝し、きたるべき年の豊穣を祈る儀式である。古代からあり、宮中では旧一一月第二の卯(う)の日に天皇自ら祭儀を行った。明治六(一八七三)年以後は一一月二三日と定められ、現在は勤労感謝の日として、勤労を尊び、生産を祝い、互いに感謝しあう国民の祝日となっている。この日、玉生神社では、氏子である大字の関係者が集まり神事が行われる。
東古泉の素鵞神社でも、毎年一一月二三日に玉生神社の宮司を迎えて関係者による勤労感謝祭の神事が行われている。
PDF版ダウンロード H30-北伊予の傳承14 [PDFファイル/10.67MB]












